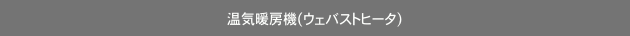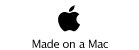戦後に機械式内燃動車と初期の液体式内燃車、それにごく少数の客車に装架されていた客室暖房に「温気暖房機」がある。
「温気暖房機」は国鉄における制式名称である。
軽油燃焼式の車両用暖房装置であるこれは、一般にはその開発元であるドイツWebast社による、エンジン独立型暖房機(すなわちエンジンの稼働を要しない暖房装置を云う)の総称的な商標名-ウェバスト(ドイツ語読みならベバスト)ヒータとして知られている。
国内では初期の液体式ディーゼル内燃車採用されてへ普及し、これをライセンス生産した五光製作所による「五光ヒータ」の方が通りが良いかもしれない。他に三国商工によるライセンス生産の「ミクニウェバスト」が在ったけれど、検修現場などでは「五光ヒータ」と通称されていたようである。
これは、初期のディーゼル内燃車ばかりでなく、同時期にガソリン機関をディーゼルに換装した機械式内燃車もその暖気暖房に替えて搭載され、一部の客車にも装架が及び、それの石炭ストーブを放逐したのだった。
戦後の国鉄は、一貫して地方線区への内燃車の投入などを通じて、そこに残る混合列車の客貨分離を推進した。しかしながら、1960年代後半に至っても、客貨ともに輸送量の小さい線区にそれは残存し、道内では石北本線と釧網本線に多くが設定されていた。
客車の暖房は、機関車からの蒸気供給を基本とするものだが、この両線区の例では、途中駅での貨車解結の利便から、それの組成を旅客車の前位方連結としていた関係上、蒸気暖房が原則的に使用出来ず、客車暖房は永く石炭ストーブ(その形状からダルマストーブと呼ばれた)によっていた。石北線では、加えて遠軽にて進行方向の変わる事情もあった。
これらの客車は、屋根に排煙管(煙突である)を設備し、冬期には一部の腰掛けを撤去しての設置のため車体に記された定員表記が夏冬で異なっていたものである。
これを代替するものとしてウェバストヒータに白羽の矢が立てられ、 1955年度の阿仁合線での試験運用を経て、要求の在る線区運用車への搭載が始められた。石北/釧網両線区の運用客車に関しては60年代に順次搭載工事が行われ、その末頃までに完了したと思われる。
内燃車の暖房も温水式に移行して久しく、この軽油燃焼式の暖房装置自体も既に陳腐化しており訝しく思ったものだが、新規投資の難しい老朽車への工事であり、またそれ以外に代案も無いゆえであったのだろう。おそらくは、この頃には用途廃止されていた機械式ディーゼル内燃車の廃車発生品と推定している。
これの搭載車は、総数は少ないのだけれど、石北/釧網本線と同様の事由に依る名寄客貨車区の深名線専用車や、内地での弘前運転区の五能線運用車の他、これも北海道内配属車に限らず、牽引機や組成方/運用などから独立暖房を必要とした一部の荷物車や郵便車にも装架例がある。
興味深いのは、工場入場車回送時の控え車として品川客車区に永く残されていたナハフ11 2018/2021/2022の3両で、当然暖房引き通しなどの無い編成組成に乗務員からの苦情があって、車掌室にのみダクトを通した温気暖房機が設置されていた。
客車の世界では広く普及したものでないためか、その趣味的研究の谷間にあって、装架車全車は把握されていないようである。
その仕組みは、原理的には現在家庭でも使われる温風暖房機(FFファンヒータ)と同様で、軽油の燃焼にて生じた高温風を利用するものである。送風機にて取り込んだ室内空気を熱交換器を経て風道にて導き、腰掛下に設けた吹出し口より室内に放出する方式と、高温空気を放熱管内に循環させて、それに設置の放熱フィンを通じて熱交換する方式の二通りがあった。燃焼排気は勿論室外に排出された。
後者では、金属板のカヴァをともなった放熱管が窓下床面に引き通される客室内の造作は、蒸機暖房や温水暖房と変わりない。
釧網本線列車での経験では、通常なら十分な暖房だが、外気温度がマイナス10度を割り込む程になると俄然効きは悪くなり、容量不足を露呈していた。極寒地向けには、やはりストーブに軍配が上がる。
乗り込んだ際の、微かな石油臭も記憶に残っていて、これは懐かしい。